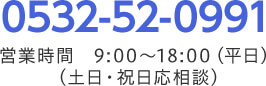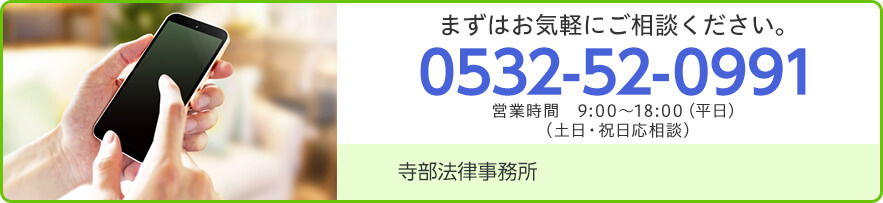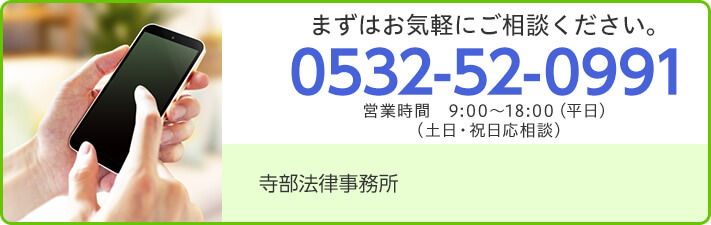1 はじめに
- 「従業員が、売上金を私的に使った」
- 「パワハラやセクハラをする従業員がいる」
- 「何度も遅刻や無断欠勤をし、注意しても改めない従業員がいる」
といった場合、使用者は、どのように対応したらよいのでしょうか。
このような場合、使用者としては、懲戒処分を検討することが多いと思います。
労働基準法から見る懲戒処分とは
懲戒処分は、企業秩序を維持するために行われる制裁罰であり、将来の非違行為を抑止する目的があります。
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない旨規定しています。
労働基準法第89条9号は、就業規則で定める事項の一つとして、「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を規定しています。
労働基準法106条は、使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない旨規定しています。
一方、労働契約法第15条は、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする旨規定しています。
懲戒処分をするには、就業規則等で定めるなどの事前の対応のほか、従業員の非違行為があった場合には、適正な手続を経たうえで、懲戒処分の内容について相当な内容であることが必要であると考えられます。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 懲戒処分の種類
(1)戒告(かいこく)
戒告とは、非行などを注意し、将来を戒めるために文書または口頭で行われる懲戒処分の一種です。
なお、企業によっては、譴責(けんせき)、訓告(くんこく)という懲戒処分をもうけている場合もあります。
戒告は、懲戒処分の類型としては、最も軽い処分と位置づけることが多いと思います。
(2)減給
給与の一定額を給与から差し引く処分です。
労働基準法第91条は、就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない旨規定しています。
労働基準法第91条に違反する減給は、無効(労働基準法第91条に違反する部分は、減給されなったものとして、使用者に支払義務が生じる)と考えられます。
(3)出勤停止
従業員が会社に出勤することを禁止する懲戒処分です。
出勤停止中の給与は、通常支給されません。
(4)降格
降格とは、役職、職位、職能資格、職務等級を引き下げる懲戒処分をいいます。
降格により、権限が剥奪されたり、役職等による手当が不支給になったりすることもあり、従業員にとって大きな不利益を伴う懲戒処分になります。
(5)諭旨解雇(ゆしかいこ)
諭旨解雇とは、従業員と話し合って、解雇する懲戒処分をいいます。
解雇予告手当は、支給されることが通常だと思います。
退職金が一部不支給になる場合もあります。
(6)懲戒解雇
最も重い懲戒処分です。
労働基準監督署長の除外認定を受ければ、解雇予告手当は、不要となります。
退職金が減額されたり、不支給になる場合があります。
労働契約法第16条は、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする旨規定しています。
3 企業が懲戒処分を行う際の注意点
(1)就業規則の整備と周知
懲戒処分を課すには、法的な根拠が必要になります。
労働契約書に懲戒処分について規定する場合もありますが、就業規則において、定めることが通常だと思います。
就業規則は、法律の定める方法によって周知することが必要です。
(2)事実関係の調査、証拠の収集
懲戒処分に相当する非違行為が存在する可能性があると使用者が認識した場合、事実関係を調査することが必要だと思います。
また、非違行為の事実を認定するための客観的な証拠を収集したり、関係者から聞き取ったりすることも必要だと思います。
関係者から聞き取る場合には、プライバシーに配慮する必要があると思います。
(3)弁明の機会
懲戒処分をする場合、懲戒処分を受ける者に対し、弁明の機会を与えることが必要です。例えば、懲戒解雇に相当する非違行為があった場合でも、弁明の機会を与えることなく懲戒処分を課すと、懲戒解雇が無効になる場合があります。
(4)非違行為と懲戒処分の内容
非違行為の内容、過去の処分歴など諸般の事情を考慮し、非違行為の内容と懲戒処分の相当性を有することが大切だと思います。
(5)懲戒処分通知書の交付
使用者が、懲戒処分を従業員に通知する場合、懲戒処分通知書を交付することが多いと思います。
懲戒処分通知書には、通常、懲戒処分の日付、内容、理由、根拠等を記載します。
4 まとめ
使用者が、従業員に懲戒処分を課した場合、従業員が、懲戒処分の効力を争い、労働審判、訴訟等の法的手続きをとる場合があります。
使用者としては、懲戒処分を課す場合には、事前に十分な検討をして、懲戒処分を行う必要があると思います。
懲戒処分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。