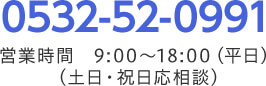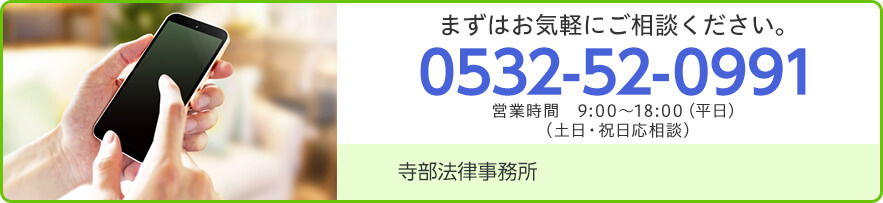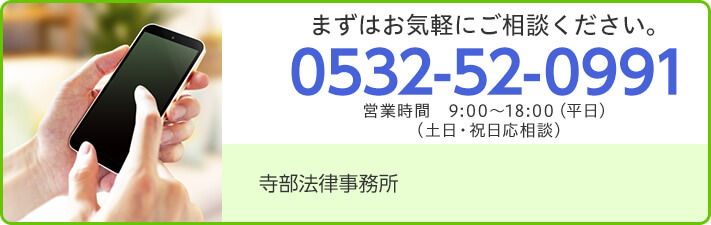はじめに
問題社員とは、一般に問題行動や能力不足等により、会社に悪影響を与える社員をいいます。
会社の指示に従わない、協調性が乏しく他の従業員と協力をして業務を進めることができない、ハラスメントをして職場の人間関係を悪くする、頻繁に遅刻をしたり、連絡なく無断欠勤をする、勤務態度が悪いなど、問題社員に対する対応に悩んでいる経営者の方もいらっしゃると思います。
問題社員がいると、真面目に働いている他の社員の士気などに悪い影響を与えることが少なくありません。一方、社員にたとえ問題行動があったとしても、解雇できるとは限りません。安易に解雇をすると、社員の側から、訴訟、労働審判などの法的手続を取られる可能性もあります。
会社にとって、従業員は、大切な財産であり、会社の競争力の源泉です。
もっとも、問題行動などをおこす従業員は、他の従業員の士気に影響を与え、会社全体に悪影響を与える場合があります。
では問題社員には、どのように対応したらよいのでしょうか。
問題社員の類型
業務の指示に従わない
会社の業務命令に従わない社員がいる場合、会社の業務が円滑に遂行できませんし、組織としての規律も維持できません。
協調性がない
会社の業務は、基本的には、一人で完結するものではありません。
社員同士協力しあって、円滑に業務が遂行できることが通常です。
協調性がない社員がいると、会社の業務が円滑に遂行できません。
ハラスメントをする
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメントをする社員がいると、社員の士気に悪い影響を与えるとともに、会社の円滑な業務運営の支障になります。
勤務態度が悪い
勤務態度が悪い社員がいると、会社の雰囲気が悪くなり、真面目に働いている社員の士気に影響する場合があります。
3 解決までの流れ
(1)初回相談
まず、面談にて、法律相談をさせていただきます。
その際、就業規則の内容、当該社員の問題となっている言動、問題行動の裏付け資料、過去の懲戒処分歴、今までの会社の対応などをうかがいます。
(2)面談でのお打ち合わせ
法律相談を重ねる中で、問題社員に対する対応について、会社の方針を決めます。
(3)問題社員の行動に対する会社の対応
社員に問題行動があったからといって、常に懲戒処分をすることができるとは限りません。
問題行動の程度が低ければ、注意、指導や始末書の提出などにとどまる場合もあります。一方、問題行動の程度が重大であれば、問題行動の程度に応じて、懲戒処分をする場合もあります。
(4)問題行動の程度が深刻な場合の解雇の検討
懲戒処分として、解雇をする場合には、会社としては、具体的に社員のどのような行為を問題行動と捉え、裏付けとなる証拠として、どのようなものがあるか、確認が必要だと思います。
問題行動のあった社員に対し、懲戒処分をする前に、弁解の機会を与えるなど、手続の適正についても、配慮する必要があります。
また、解雇が相当と思われる事案であっても、後の訴訟のリスクを考慮して、解雇手続をとる前に、退職勧奨を行う場合もあります。
(5)解雇通知
会社の方針が解雇となった場合、問題行動のあった社員に対し、解雇を通知します。
4 弁護士に相談すべき理由
法的観点からのアドバイス
弁護士に相談をすれば、法的観点から、アドバイスを受けることができます。
例えば、解雇が相当と考えられる問題行動があったとしても、問題行動のあった社員に弁明の機会を与えることなく、懲戒処分として解雇すると、後に、当該社員が訴訟等の裁判手続をすると、解雇の効力が否定される場合もあります。過去の裁判例では、懲戒処分について、手続の適正も求められています。
このように、弁護士に相談をすれば、法的観点からアドバイスを受けることができます。
社長の個人的な一時の感情によって、社員に懲戒処分や解雇を行うと、後に、訴訟になった時に、懲戒処分や解雇の効力が否定される場合もありますので、注意が必要です。
解雇や懲戒処分を法的根拠に基づく手続で行うことができる
解雇、懲戒処分について、社員に問題行動があったからといって、当然にすることができるものではありません。懲戒処分を行うには、前提として、就業規則等の法的根拠となるものが必要です。
また、就業規則は、周知することが必要です。就業規則が存在するものの、社員が就業規則の内容を知ることができない状況で、会社が保管していても、通常、会社は、従業員に対し、就業規則の拘束力を主張できないと考えられます。
また、懲戒処分を課す場合、社員に弁明の機会を与えるなど、適正な手続によって懲戒処分をすることが必要になります。
このように、懲戒処分を行うに当たっては、法的根拠や手続の適正が求められます。
弁護士に相談をすれば、法的根拠や手続の適正について、説明を受けながら、手続をすすめることができます。
自信を持って問題社員対応を行うことができる
問題社員に対し、法的にどのように対応することができるのか、悩んでいらっしゃる中小企業経営者の方は、少なくないと思います。
弁護士から、労働基準法、労働契約法、過去の裁判例などについての説明を受けながら、弁護士に自社の就業規則の内容を説明し、相談を重ねながら、問題社員に対応をすれば、自信を持って問題社員に対応できることが少なくないのではないでしょうか。
また、訴訟や労働審判になった場合でも、弁護士は、代理人として、訴訟や労働審判に対応することができます。
5 弁護士費用
相談料
初回相談無料。
2回目以降は、30分ごとに5500円。
労働審判
着手金 38万5000円
報酬金 当方の得た経済的利益の17.6パーセント
(最低額38万5000円)
(注)名古屋地方裁判所豊橋支部以外の裁判所に出頭する場合、出張費がかかります。
訴訟
着手金 経済的利益の8.8パーセント
(最低額33万円)
出廷日当 第4回目の期日から1期日当たり5万5000円
報酬金 当方の得た経済的利益の17.6パーセント
(最低額33万円)
(注)着手金の経済的利益は、当方が原告の場合、請求額、当方が被告の場合、請求をされた額になります。
報酬金の経済的利益は、当方が被告の場合、相手方の請求額から減った額になります。
名古屋地方裁判所豊橋支部以外の裁判所に出頭する場合、出張費がかかります(ただし、WEB会議の期日の場合には、出張費はかかりません)。
まとめ
問題社員対応については、労働法規についての法的知識なども必要になります。
お早めに弁護士までご相談ください。