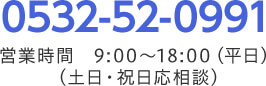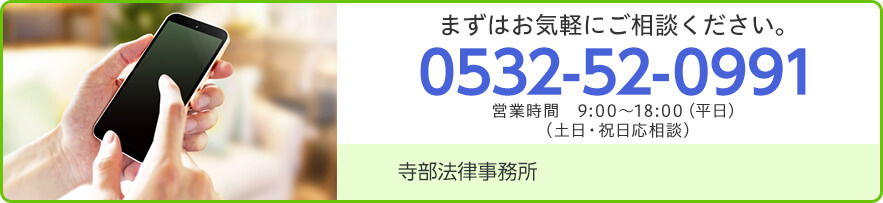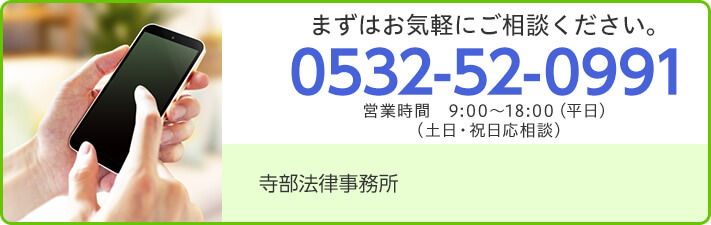1 はじめに
企業間の取引において、契約書を締結することはしばしばあると思います。
契約書は、双方の当事者が記名、押印した場合、原則として、契約書に記載されている内容は、当事者を拘束します。
取引先との間で、実際にトラブルが発生した場合、契約書の文言が大きな意味を持つことが多いと思います。
契約書を締結するにあたっては、十分に内容を検討したうえで、押印する必要があると思います。
2 秘密保持契約
(1)秘密保持契約
事業を営んでいるなかで、自社の重要な情報を、取引の相手方に対し、開示する必要が生じる場合があります。
そのような場合に、取引先との間で、秘密保持契約を締結する場合があります。
例えば、A社とB社が互いに秘密情報を開示する場合、開示する情報について、相手方に秘密を守ってもらうために、秘密保持契約を締結する場合があります。
ここでは、秘密保持契約において、定めることが多い一部の条項について、簡潔に説明します。
もっとも、秘密保持契約は、個別の事情に応じて契約条項を定めることが重要だと思います。具体的な秘密保持契約の契約書の作成や秘密保持契約書のチェックについては、弁護士までご相談ください。
(2)契約の目的
契約の目的を定める場合が多いと思います。
(3)秘密情報の範囲
秘密情報とは何かを明記することが通常です。
秘密と明示した情報に限るのか、秘密と明示しなくても、相手方当事者から受領した一切の情報が秘密情報にあたるのかなど、どのような情報が秘密情報に該当するのか、規定します。
また、秘密情報にあたらない情報についても、規定することが通常です。
例えば、開示を受けた時点において、既に公知になっている情報は、秘密情報に該当しない旨の規定を設ける場合があります。
(4)秘密保持義務
秘密保持契約では、秘密保持義務を規定することが通常です。
また、秘密情報を目的外に使用することができない旨を規定することが通常です。
また、例えば、裁判所の裁判に従い必要な範囲で情報を開示することができるなど、秘密保持義務の例外規定を定めることが多いです。
(5)情報が漏洩した場合の措置
事故その他の事情により、秘密情報が漏洩したことが判明した場合、相手方当事者に対し、直ちに報告する等、秘密情報が漏洩したことが判明した場合の具体的な措置を定めておく場合があります。
(6)損害賠償義務等
当事者の一方が秘密保持契約に違反した場合には、相手方は、違反した当事者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる旨定めることが通常です。
損害賠償の範囲について、具体的に定める場合もあります。
秘密保持契約に違反した相手方に対する差し止め請求を規定する場合もあります。
(7)複製の制限
秘密情報を開示する場合、相手方が複製をすることを制限する条項を入れる場合もあります。
秘密情報の開示を受けた側からすれば、コピーができたほうが、業務効率があがる場合があります。一方、秘密情報を開示した側からすれば、コピーを制限した方が、情報漏洩のリスクは少なくなると思われます。
秘密情報のコピーの可否や、仮に、秘密情報のコピーを制限する場合、具体的な制限の内容を記載する場合が多いと思います。
(8)不保証
秘密情報を開示した側が、相手方に対し、秘密情報について、その正確性を保証しない旨を規定する場合があります。
(9)知的財産権
知的財産権とは、特許権、著作権などの権利をいいます。
秘密情報に知的財産権が含まれている場合、秘密情報の開示によって、秘密情報を受け取った側に知的財産に関する権利が移転するものではない旨を規定する場合が多いと思います。
また、秘密情報を受け取った側が、秘密情報をもとに、新たな発明をした場合、知的財産権について、どのように取り扱うか、定める場合もあります。
(10)有効期間
秘密保持契約には、有効期間を規定する場合が通常だと思います。
また、契約期間の自動更新について規定する場合もあります。
(11)秘密情報の返還等
契約が終了した時点において、情報を開示した側から、相手方に対し、秘密情報の返還や破棄について、規定することが多いです。
また、契約途中であっても、秘密情報の返還や破棄を求めることができる旨を規定する場合もあります。
秘密情報の返還や破棄の具体的な方法について、規定することが多いと思います。
(12)契約終了後も存続する条項
秘密保持契約は、秘密を守ることを目的とする契約ですので、契約が終了したからといって、全て終わりにならないことが多いです。
秘密保持契約の期間が満了した後も効力を有する条項について、規定する条項を入れることが多いです。
(13)権利義務の譲渡の禁止
秘密保持契約の当事者としての権利、義務について、第三者への譲渡を禁止する旨の条項を定める場合があります。
(14)管轄の合意
当事者間で紛争が生じた場合には、どの裁判所で裁判を行うか、管轄の合意の条項を入れる場合も少なくありません。
3 秘密保持契約書の作成、チェックを弁護士に依頼するメリット
秘密保持契約書の作成、チェックについて、弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
弁護士は、紛争の交渉、訴訟などを経験しています。弁護士に秘密保持契約書の作成やチェックを依頼することにより、契約書に記載した各条項の意味や、契約内容についての法的リスクについて、助言を受けることができます。
一方、弁護士に依頼すると、費用がかかります。
もっとも、秘密保持契約書の各条項の意味や法的リスクについて、把握することは重要なことだと思います。
秘密保持契約書について、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
4 まとめ
寺部法律事務所では、契約書の作成、チェックや顧問業務を取り扱っています。 秘密保持契約について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。